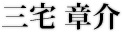切妻屋根の痕跡のための類型学 Typology for Traces of Gable Roofs
2021.2.23 tue- 3.7 sun
京都写真美術館ギャラリー ジャパネスク

京都のそここで老朽化した町家が取り壊され、空き地が出現している。
空き地に面した建物の外壁にはかつてあった隣家の屋根の痕跡が刻まれている。
その屋根の下で営まれていたかもしれない日々の暮しを偲ばせる。
5年前に父が他界し、神戸の実家を処分した。昭和30年代に摩耶山のふもとを切り拓いて建てたものだ。今は更地となり、新しい住宅が建てられ、かつての面影はまったくない。未練なく、綺麗さっぱりなくなっていることを爽快に思う半面、これが京都だったらという思いもよぎる。
僕は伝統的な京の町並みの風情が失われ、無残な姿を晒していることに、正直言ってあまり抵抗感がない。むしろ、インバウンド需要を狙って、厚化粧をほどこし、テーマパーク(見世物)化することにこそ、親の遺産を切り売りしているような、あさはかさを感じている。
人も町も、生きておればこそ、時に醜態を晒すものだ。時の流れの中で人の営みの痕跡が重なり、その層のところどころが綻びて、まるでパッチワークの様相を呈している。
むしろ、そんな京都に僕は惹かれる。
会場風景





推薦文
何か、子供の頃遊んだ空き地に再会したような、失われた故郷が夢の中で立ち昇ったような感情が抑えられない。
三宅章介の写真集「切妻屋根の痕跡のための類型学」のページをめくる事は、家族アルバムを見るよりも心を動かされる。一人っ子の私にも、兄や弟がいたような不思議な気分である。初めてシンクロニシティを信じる気になってしまった。
実は、私も痕跡に惹かれて、写真を撮っている。だから余計我が事のように、シャッターを切る心情に共感するのかもしれない。
もちろん、三宅章介の写真は、時代の残滓を露呈する作品ではない。かつてそこにあったという、写真が抱えるメディアの特性がテーマである。あらゆる写真は遺影である。今ある記念写真、人物写真は、50年も経てば直ぐに時代の雰囲気を伝える資料に変容する。三宅章介が提示する作品が愛おしく思えるのは、街が遺影である事を表現しているからに他ならない。
そしてもう一つのテーマ、見えないものを見ようとする描写の中に、視覚偏重への疑問が深沈と流れている。それが、愛おしさを生むのである。痕跡が触発する消失した建造物のリアリティー。見えない、喪失したものを幻視させる描写力。
三宅章介の写真の魅力は、メタメディアの構造にあるのだ。この、見えないものを見せる三宅章介の姿勢こそ、わたしたちが今最も必要としているテーマだという事は言うまでもない。
多摩美術大学名誉教授
前橋文学館館長
萩原朔美
京都新聞展評 2021.2.27朝刊
写真家・三宅章介の作品を初めて見る人は面食らうかもしれない。同じモチーフ、同じ構図の作 品が延々と並んでいるからだ。 三宅のテーマは「痕跡」である。古い木造家屋が解体された後、隣家の壁にそのシルエットが残 される。古い建物が多い京都市内では見慣れた光景だろう。彼は約3 年にわたりそれらを取材し、 精選した 120 点を展示している。 物質をその特徴ごとに分類・考察する学問をタイポロジー(類型学)といい、三宅はその手法を 自作に応用している。そして、写真作品にこの手法を用いた代表的作家は ,1970年代のドイツ で活躍したベルント&ヒラ・ベッヒャー夫妻だ。 夫妻は工場や給水塔など近代の工業的建造物をタイポロジーの手法で撮影し、ドイツ近代史を振 り返るとともに、コンセプチュアル・アートやミニマル・アートとしての写真表現を確立した。 この観点から三宅の作品を見ると、彼の狙いが見えてくる。京都から失われつつある伝統的な家 並みや、そこで暮らしていた人々の営み、さらには時代や価値観の変遷といったものまで写し取 ろうとしていうるのだ。 また、写真に写ったものはすべて過去(撮った瞬間から過去になる)という特性から見ると、彼の 作品には撮影時点での過去と、被写体が醸し出すさらなる過去という二重構造が潜んでいるこ とになる。このあたりまで気を配って鑑賞すれば、本作品の奥深さが分かるだろう。
小吹隆文・美術ライター